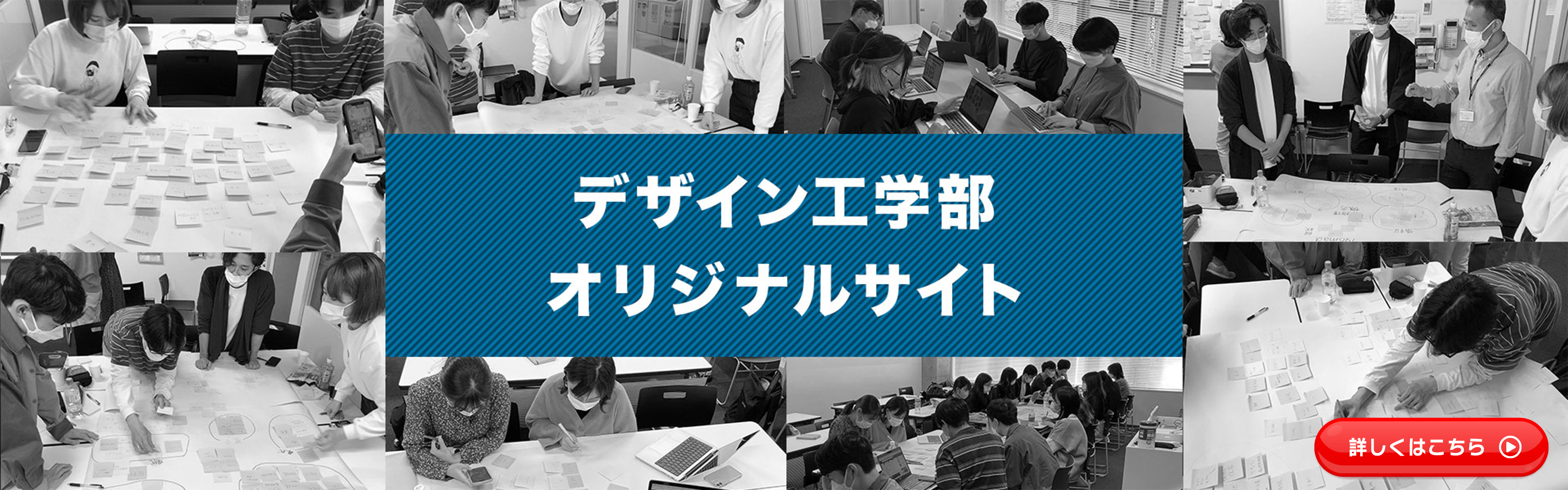デザイン工学部
「当たり前を疑い、共感を生み出す」デザイン人材の育成
現在の社会は多様化かつ複雑化し、SDGsなどの困難な課題が山積しています。また、デジタル技術を始めとする技術の進展は日進月歩であり、その変化の激しさに人々は戸惑っています。一方で、多くの製品やサービスは成熟し、利用者は特に不便や問題を感じているようには見えません。そのような時代においては、課題を発見し解決して行く力に加えて、まだ具体化していない未知の課題を想像し、新たなアイデアや方向性を提案できる人材が求められます。
デザイン工学においては、まず対象(利用者や社会)を観察し、対象に共感することで未知の課題を想像し、課題に対する解決法・アイデアを考案(デザイン)します。次に工学的な技術を用いてアイデアを実装します。それを実際に利用してもらい、対象にとって課題が解決したかを評価します。このプロセスを何度も繰り返しながら、より良い方向に高めて行くことがデザイン工学の考え方です。
デザイン⼯学部は、現実の課題発⾒と解決のみならず、未知の課題を想像し、新たなアイデアを提案することで、より良い社会を追求できる⼈材の育成に取り組みます。
コース紹介
デザイン工学科には3つのコースがありますが、デザイン工学のプロセスはどのコースでも共通です。コース間の違いが出るのは、主に実装技術の部分です。このため主に専門科目とそれに関連する共通科目の部分で、コースで履修すべき科目が変わってくることになります。コースとして推奨する科目履修例を提示するので、基本的にはこれに従って履修することになりますが、一部履修人数が制限される科目を除いて、どのコースの学生も任意の科目を履修することは可能です。
就学キャンパス
1・2年次/大宮キャンパス 3・4年次/豊洲キャンパス
デザイン工学部の特徴
カリキュラムの特徴
デザイン工学科の科目群は、共通科目、専門科目,プロジェクト科目から構成されています。共通科目は、対象(利⽤者や社会)の視点から課題を想像するデザイン思考⼒を育成する科目です。社会の多様性を理解し、また多面的に物事を考えるための教養や倫理感を身に付けるため「教養科⽬」「英語科⽬」「産業・社会科⽬」があります。またデザイン対象としての人間を理解し提案するための「人間中心科目」,対象や評価結果の分析ならびに専門科目の基礎となる「データ・サイエンス科目」があります。デザイン工学のプロセスを進めるための手法を学び、実際に使ってみる「リサーチ科目」も共通科目に含まれます。
専⾨科⽬は、アイデアを検討し、具現化(実装)するための科目です。「デザイン科⽬」は、アイデアを深め、意匠的に表現することで具体的イメージを提示する力を養います。形のあるアイデアを実際の製品として実現するための専門知識を修得する「⽣産⼯学科⽬」、形のないアイデアをソフトウェアで実現するための「ソフトウェア科⽬」、実際の動作をともなうものを実現するための「知能・制御科⽬」があります。特にデザイン科目の「デザイン基礎演習」とソフトウェア科目の「情報処理入門」は、デザイン工学のプロセスにとって必須のものであり、学科全体の必修科目となっています。広い意味でのデジタル技術は,この専門科目により養われます。
プロジェクト科目は、共通科⽬と専⾨科⽬で修得した⼒を実際に試してみる、実践型教育の場を提供します。一般には「卒業研究」と呼ばれる科目であり、デザイン工学科では3年生からこれに取り組みます。プロジェクト科目や他の多くの演習科目を通して、協創する力を身に付けることができます。
学年進行と研究室配属
年次進行にあわせて基礎的な科目は低学年次に、専門性や応用性の高い科目は高学年次に配置されています。1年前期では基礎的な科目が多く、結果的に3コースともに共通の科目が多くなります。1年後期から徐々に専門性のある科目が増えていきます。2年次では専門分野の基礎となる科目が増え、これらを学ぶ中で自分にあった専門性を理解し、修得して行くことが期待されます。
3年次では、最初のプロジェクト科目が始まり、いわゆる研究室配属があります。研究室の担当教員のアドバイスを受け、自分の専門性にあった科目を履修します。なお、自分の専門性について考え研究室配属に備えるために、1年後期「ラボ探究」と2年後期「ラボ探訪」があります。このように、様々な研究分野を知ることができるようにシラバスが設計されています。
4年生の総合プロジェクトは、3年間修得した知識を実践的に使うことで本当に自分の力とするための集大成の科目です。これによりディプロマ・ポリシーを満たす力を身に付けることができます。
教育研究上の目的・3つの方針
デザイン⼯学部は、より良い社会を追求するために、現実の課題発⾒と解決のみならず、未知の課題を想像し、新たなアイデアを提案できるデザイン⼯学技術者を養成します。そのために、教育プログラムを通じて、デザイン思考・デジタル技術・協創の3つの能⼒を育成します。
デザイン⼯学部は、現実の課題発⾒と解決のみならず、未知の課題を想像し、新たなアイデアを提案することで、より良い社会を追求できる⼈材の育成に取り組みます。そして、以下の能⼒を⾝に付けて卒業要件を満たした者に、学位を授与します。
- 専⾨教育の修得に必要な基礎学⼒・教養⼒
- 常識に囚われず疑問を持ち、利⽤者の視点から課題を想像できるデザイン思考⼒
- 社会実装を念頭にアイデアを提案し、具現化できるデザイン⼯学の専⾨知識とデジタル技術⼒
- 多様な意⾒を積極的に収集し、⾼い倫理観を持って課題解決に向けて他者と協働できる協創⼒
デザイン⼯学部は、ディプロマ・ポリシーに掲げる能⼒を⾝に付けるため、以下の教育課程の編成、教育内容・⽅法と学修成果の評価に基づいた教育を実施します。
教育課程の編成
デザイン⼯学を体系的に学修できるよう、教育課程を「共通科⽬」「専⾨科⽬」「プロジェクト科⽬」に区分し、科⽬を以下のように配置します。
共通科⽬は、「教養科⽬」「英語科⽬」「⼈間中⼼科⽬」「産業・社会科⽬」「データ・サイエンス科⽬」「リサーチ科⽬」の細区分で構成します。専⾨科⽬は、「デザイン科⽬」「⽣産⼯学科⽬」「ソフトウェア科⽬」「知能・制御科⽬」の細区分で構成します。
教育内容・方法の実施
全体
- デジタル技術⼒と協創⼒を育成するため、いずれの区分においても演習または研究を軸とした実践型教育を実施します。
- カリキュラムツリーを⽰し、学修・教育到達⽬標に応じた科⽬履修の理解を促します。
共通科⽬
- 常識に囚われず疑問を持ち、利⽤者の視点から課題を想像するデザイン思考⼒を育成します。
- 教養科⽬、英語科⽬、産業・社会科⽬:多様性を理解し、社会の様相や動向を踏まえた上で、多⾯的に物事を勘案するための教養・倫理観を育成します。
- ⼈間中⼼科⽬:利⽤者の視点から物事を勘案する能⼒を育成します。
- データ・サイエンス科⽬:デジタル技術を中⼼とする、⼯学と情報処理の専⾨知識修得に必要な基礎学⼒を育成します。
- リサーチ科⽬:複眼的かつ論理的に物事を勘案し、未知の課題を想像する能⼒を育成します。
専⾨科⽬
- 専⾨知識を体系的に学び、アイデアを検討し具現化するための技術の修得を促します。
- 他者の背景を理解し協創を促すため、他分野の専⾨知識を学修する機会を設けます。
プロジェクト科⽬
- 共通科⽬と専⾨科⽬の学修によって⾝に付けた能⼒を発揮する機会として、研究による実践型教育を実施します。
学修成果の評価
- 知識や技術の理解度・習熟度、能⼒の達成度などの学修成果を、試験や課題に対する成果、ルーブリック、それらの組み合わせなどによって評価します。
- 単位制を採⽤し、学修・教育到達⽬標と各授業科⽬の達成⽬標に対して、学修成果が⼀定のレベルに達した際に単位を付与します。
デザイン工学部は、現実の課題発見と解決のみならず、未知の課題を想像し、新たなアイデアを提案することで、より良い社会を追求できる人材の育成に取り組みます。そのために建学の精神、デザイン工学部の教育・研究の方針と内容をよく理解し、大学が求める人物像に加え、以下に当てはまる人物を求めます。
デザイン⼯学部が求める⼈物像
- ・デザイン工学部での学修・研究を強く志望し、関連する教育分野の基礎学力を身に付けた人
・社会へ貢献する意欲と、旺盛な好奇心を追求できる人
・新たなアイデアをデジタル技術で実現することに興味を持ち、積極的に新たな分野を学ぶことに躊躇しない人
・自分とは異なる考えを持つ人々と協働し、失敗を恐れることなく挑戦してきた人 - 上記に賛同し、本学への入学を志望する人は、高等学校等において以下能力等を身に付けておくことが望まれます。
(1)高等学校等の課程で学ぶ知識・技能(特に外国語、数学、理科)
(2)思考力・判断力・表現力等の能力
(3)主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度 - 本学部においては、上記の能力等を総合・多面的に評価するため、以下の入学者選抜を実施します。
・ 一般入学者選抜の前期・後期・全学統一日程入試では、(1)を重視するとともに、筆記試験、外部試験により(2)を評価します。
・一般選抜の大学入学共通テスト利用方式では、多科目の成績により(1)及び(2)を評価します。
・総合型選抜では、記述試験や外部検定試験等により(1)及び(2)を評価し、面接や口頭試問などにより(1)及び(2)、(3)を総合的に評価します。
・学校推薦型選抜では、調査書で (1)及び(2)を評価し、面接で (1)及び(2)、(3)を総合的に評価します。